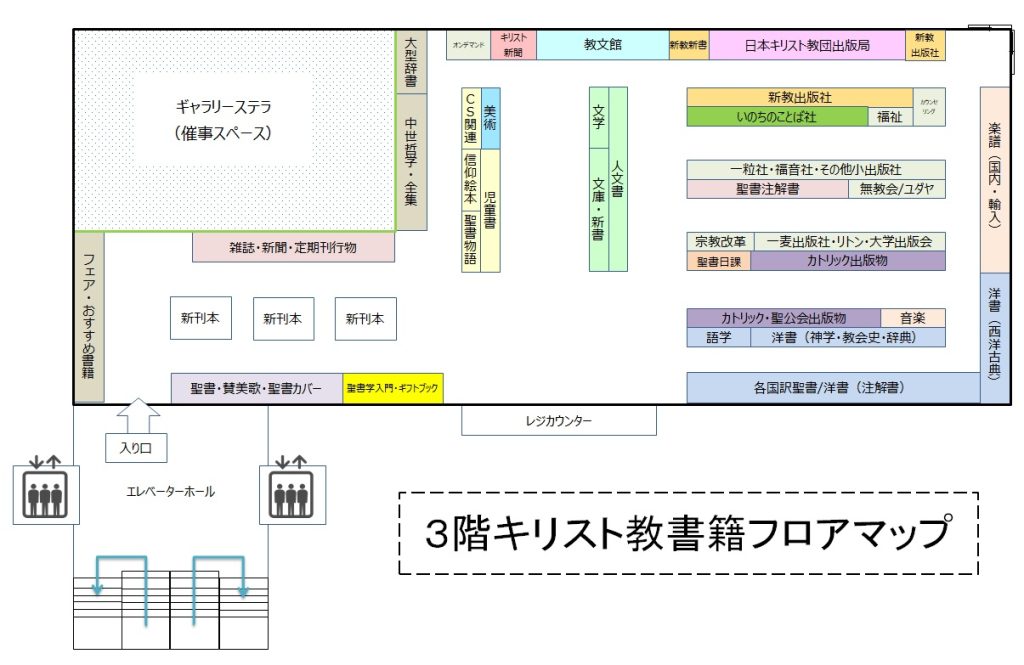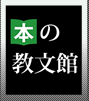※在庫状況についてのご注意。
内容詳細
著者は「宗教間対話」を主題とするフランクフルト大学主宰の集中講義を行った。日本社会の「和」についての講義に対する,学生や教授陣,市民など多くのドイツ人受講生との質疑応答を通して,日本とは違い,個人の主体性や社会倫理を重んずるキリスト教文化圏の特徴を痛感した。
今日,価値観や宗教観が多様化し,交通手段や情報システムの発達で異文化圏の人々が互いに交流する機会が増えた。それとともに社会的な危機意識が高まり,異文化間における対話の重要性が強まっている。本書は社会の規範を支える「宗教」の力と,個人をつなぐ「和」の原理を,キリスト教を踏まえて分かり易く叙述する。個人や社会,そして宗教に関心のある読者には必読の一書である。
第Ⅰ部では,諸宗教が共存するわが国の特殊な文化的風土を考察する。日本の民族宗教である神道,日本化した仏教,政治哲学の流れで受容された儒教,戦国時代のキリスト教宣教師やキリシタンへの迫害,細川ガラシアや「日本のシンドラー」と呼ばれた杉原千畝など,多くの事例をもとに,日本と宗教の関わりを考える。
第Ⅱ部では,宗教を生活の視点から見直す。日本人として相応しい人間像と宗教の関わり,倫理観や死生観,そして高齢者や「いのちの選別」という現代的な問題を扱う。
第Ⅲ部では,フェミニスト神学,ヒロシマ・ナガサキ・フクシマの平和構築,諸宗教とキリスト教との対話などから,わが国が抱える宗教の役割や問題点を明らかにする。
著者はキリスト教をはじめ,わが国の宗教を広範に考察して,「和」と信心とともに生きてきた日本人の姿を通して「宗教の意味」や「人間とはなにか?」を問いかける。
【目次】
はじめに
第Ⅰ部 諸宗教が共存する日本という文化
第一章 諸宗教の共存する文化土壌
1 外来普遍宗教の日本的受容の様態
2 神道――神聖視される国家共同体と家族共同体の創出
3 日本化した仏教――王法護持と非出家主義
4 儒教――「家」制度及び封建制度安定化のイデオロギー
5 新宗教――その保守的共同体の社会観の継承と性別役割の正当化
6 宗教的ルーツをもつ「和」の社会日本とキリスト教
第二章 キリスト教の日本的展開及び海外で知られたクリスチャン
1 キリスト教の日本的展開
(1)「キリシタンの世紀」(1549-1638)とフランシスコ・ザヴィエルによる土着文化・習俗に適応した宣教
(2)教会・共同体の形成
(3)宣教のあり方と入信の動機
(4)巡察師アレッサンドロ・ヴァリニァーノと土着文化摂取というイエズス会宣教のクライマックス
(5)キリシタン禁止令と迫害
(6)開国と新たな宣教の始まり
2 細川ガラシア(1563-1600)の虚像と実像
(1)ガラシアの生い立ち
(2)キリスト教への道
(3)ガラシアの死
(4)ガラシアのイメージと評価――西洋と日本
3 杉原千畝(1900-86)の挫折と栄光
(1)6000人のユダヤ人を救った経緯
(2)杉原の行為に対する評価と日本政府との和解
第Ⅱ部 宗教を生活の視座からとらえる
第三章 日本文化においてどのような人間が望まれるのか?
1 神道文化の脈絡で「人間になる」とは?
2 儒教文化の脈絡で「人間になる」とは?
3 仏教文化の脈絡で「人間になる」とは?
4 「関係性」重視の日本社会において「人間になる」とは?
5 日本社会での人間像の形成――キリスト教は日本宗教の補完かアンチテーゼか?
6 理想の人間像とは?――日本とドイツの例
第四章 日本人の倫理観とキリスト教倫理
1 日本的倫理観の宗教的脈絡
2 近代化プロセスにおける倫理の形成
(1)日本の近代化の条件としての諸宗教
(2)日本の諸宗教における「神的存在」とは何か?
3 倫理的行為の規範
4 近代化における政治倫理
5 近代化における経済倫理
6 日本人の倫理観再考
7 世俗化した現代社会における倫理と宗教の意味
8 付編 責任とは何か? 良心とは何か?
第五章 死生観
1 神道の伝統における「死」
(1)記紀神話における「死」の原体験
(2)神道における「死」の省察
2 仏教における「死」
(1)原始仏教における「死」
(2)大乗仏教における「死」
3 自死
4 倫理的に再考する「死」及び死者の意味
5 付編 「いのちの選別」再考
(1)優生学の問題
(2)フェミニズムと宗教の視点からの提言
第六章 高齢者問題は,成熟社会の試金石か
1 宗教伝統から見る「老い」
2 なぜ「老い」が現代社会で問題とされるのか?
3 ジェンダー視点で再考する「老い」
4 スティグマ化(負のレッテル貼りを)された「老い」
(1)宗教伝統における「老成」の思想を再考
(2)社会と人間の成熟のために「弱さ」の力/意味を再発見
5 「老い」の問題化は社会の成熟度のバロメーター
(1)高齢者の「もうできなくなった」現象を再考
(2)ケアの本質を再考
(3)高齢者問題の未来を拓くために
第Ⅲ部 現代社会での宗教の意味を問う
第七章 フェミニスト神学から日本人が学べること
1 日本人のフェミニズム意識
(1)母性と家族をめぐる論争
(2)1970年代のリブ運動
2 日本における「男尊女卑」観の成立
(1)神道――アマテラスを理想とする女性観
(2)仏教――女性の不浄性と罪障性を刻印
(3)儒教――「家」制度と「性の位階」を確立する根拠
3 日本におけるフェミニスト神学の受容
(1)神学者エリザベート・ゴスマンの数奇な運命
(2)ゴスマンの学術的功績
( 3)宗教間対話
4 人間(男女)理解の非対称性――東西の相似と相違
(1)東西思想の相似
(2)相違点は何か?
5 日本の現代の問題に対峙して
第八章 平和構築――ヒロシマ・ナガサキ・フクシマを体験した国からのコンセプト
問題の所在
1 平和概念の再考
(1)古代イスラエルの平和概念のダイナミズム
(2)「ローマの平和 Pax Romana」に含意される暴力性
(3)「キリストの平和」非暴力の教え
(4)ローマ帝国内のキリスト教会における「正戦」概念の受容
(5)現代キリスト教会からの「記憶と和解」のメッセージ
2 日本の歴史・社会文化の文脈における平和/和解
(1)日本との比較で再考するドイツ戦後史
(2)ヒロシマ・ナガサキ後の平和論とその陥穽
(3)日本の社会倫理の特性
3 記憶と和解の宗教倫理
(1)「山上の説教」における非暴力の教え
(2)「善きサマリア人」の譬え(ルカ10・25-37)
むすびにかえて――記憶と和解の構造
第九章 日本の諸宗教とキリスト教との対話史
1 初期宣教時代の対話
(1)不干斎ハビアンとは?
(2)『妙貞問答』とは?
(3)背教者となったハビアンの書『破提宇子(ハデウス)』とは?
(4)ハビアンの歩みの軌跡
2 近代文学者によるキリスト教の棄教
3 キリスト教以外の諸宗教に対する現代カトリック教会の姿勢
4 東日本大震災/フクシマ原発事故を契機とする諸宗教からの声明
5 現代での宗教間対話・協働の試み
おわりに
索引