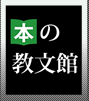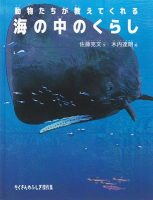
【たくさんのふしぎ40th】🤔 (2017年8月号)
『動物たちが教えてくれる 海の中のくらし』
佐藤克文 文
木内達朗 絵
福音館書店 刊
2020年10月10日 発行
1430円(税込)
40ページ
海の動物たちの謎を探求する、バイオロギングの入門書
皆さんは「バイオロギング」という言葉を知っていますか? これは人間が直接観察することのできない海中の動物に小型の記録計を取り付けて、動物自身に行動データをとってもらう手法のことです。1960年代から始まった記録方法ですが、目覚ましい技術開発のおかげで今では人差し指ほどのサイズにまで小型化され、つけられる動物たちの負担も減ったことでより自然に近い行動が記録できるようになっています。バイオロギングで得られたデータから、どんなことがわかってきたのでしょうか。
水生動物を研究している著者は、子育て中のウェッデルアザラシにカメラや加速度センサーをつけて氷の下でどのような行動をとっているのか調べました。ウェッテルアザラシは300メートルの深さ(東京タワーと同じくらい)まで潜ると知られていましたが、子育て中の母アザラシは深い潜水はせずに海面下5~10メートルほどのところで子どもに泳ぎを教えていることや、授乳によって体重が半減する頃にようやく300メートルまで潜ってエサをとることなどが観察されました。さらに著者はアザラシがどのようにその深さまで泳いで行っているのかも調査します。すると、体重が重い時と軽い時では泳ぎ方に違いがあることがわかってきたのです。アザラシたちは重力と浮力の影響を最大限利用し、負荷を最小限にするための泳ぎ方や泳ぐ速さをしていることがバイオロギングで証明されました。様々な種類・個体の水生動物(90トンのシロナガスクジラから500グラムのウトウまで)を調べることで、体の大きさの違いに関わらず、動物たちが呼吸をするための水面とエサがある海の深いところとを往復する時の泳ぐ速さがごく狭い範囲に収まっており、それが最も効率の良い泳ぎ方であることが分かったのです。
分からないことを知りたいという強い思いが発端となり、研究者たちが工夫と苦労を重ねたおかげで水生動物たちの知られざる暮らしが見えてきました。技術がもっと進めば今後、さらなる発見も増えていくでしょう。そして、それが新たな疑問を生むという果てしない繰り返しで、学問はますます発展していくのです。海の中にはまだまだ謎がたくさんあります。この本を読んだ子どもたちが、著者のあとに続いて新発見をする日もそう遠くないかもしれません。(か)
★ご注文、お問い合わせはお電話、Fax、メールにて承ります★
売場直通電話 03-3563-0730
Fax 03-3561-7350
メールでのお問い合わせは下記のフォームからどうぞ。