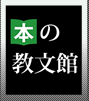【たくさんのふしぎ40th】🤔(1989年12月号)
『本のれきし5000年』
辻村益朗 作
福音館書店 刊
1992年10月1日 発行
1430円(税込)
40ページ
「本」はどうやって今の形になったのかーー
このページを読んでくださっているあなたは、きっと読書が好き、もしくは本に興味のある方なのでしょう。最近、どんな本を読みましたか? 今、手元にはどんな本がありますか?
一口に「本」と言っても、それがどういう性質のものを指すのか説明するのは難しいものです。判型やページ数は様々ですし、大量印刷されたものから1冊ずつ手作りされたものなど多岐にわたります。共通しているのは、それらのほとんどは紙に書かれているということ。では紙の発明以前、人々は何を使っていたのでしょう? 本の5000年にも及ぶ歴史を遡る旅がはじまります。
古くエジプトでは、植物のパピルス草を使って巻き物状にしたものにヒエログリフという象形文字で物事を書きつけていました。なかでも、大英博物館に収蔵されている『死者の書』は3150年ほど前に作られた有名な1巻ですが、そこには物語性のある着彩された絵が並び、文字を読めない私たちにも当時の人々が考えていた死後の世界を想像して楽しむことができます。メソポタミアでは粘土板にアシのくきで楔形文字を押しつける方法が、その後の紀元前2世紀のエジプトでは羊皮紙が登場して次第に文字を記録する方法が改良されていきます。
一方、3000年以上前の中国でも動物の骨、木や竹のふだに文字を書き記していたことがわかっています。しかしそうしたふだ(木簡、竹簡)には重さがあり、たくさんの人が読むことを想定すると不便です。そこで生まれたのが、紙でした。それぞれの時代や文化に根差した素材と道具を駆使して文字を伝え残すには、人々の試行錯誤はもとより情熱が欠かせなかったことでしょう。
本書では、この後にも現代につづく発明が細かく書かれています。ここで種明かししてしまうのは、それこそ「本」を読む楽しさを奪ってしまうというもの。ぜひ本書を開いてみてください。複雑かつ精緻な印刷や製本過程までもを知ることで、人は真の読書家になるのかもしれませんよ。 (い)
★ご注文、お問い合わせはお電話、Fax、メールにて承ります★
売場直通電話 03-3563-0730
Fax 03-3561-7350
メールでのお問い合わせは下記のフォームからどうぞ。